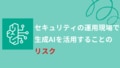サイバーセキュリティのリスクとは?安全なデジタル環境を構築するために
はじめに
近年、パブリッククラウドサービスの普及に伴い、サイバーセキュリティのリスクが急増しています。現代のビジネスや個人の生活において安全にクラウドを活用していくには、サイバーセキュリティは非常に重要なテーマであると言えるでしょう。
本記事では、情報漏洩やマルウェア攻撃等のサイバーセキュリティのリスクに関する基本的な考え方を解説しつつ、すぐにでも実施できる具体的な対策をご紹介します。
そもそも、パブリッククラウドとは?
パブリッククラウドは、インターネットを介して多数のユーザーに提供されるクラウドコンピューティングサービスです。代表的なサービスには、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloudなどがあります。ユーザーはこれらのサービスを利用して、データの保存やアプリケーションの実行、コンピューティングリソースの利用などを行うことができます。パブリッククラウドサービスは高いスケーラビリティやコスト効率の良さから、多くの企業で採用されています。
しかし、使いやすさの一方で、セキュリティリスクも考慮して活用しなければなりません。
サイバーセキュリティの知っておくべきリスク
サイバーセキュリティリスクとは、インターネットやネットワークを通じてシステムやデータが攻撃される可能性のことです。万が一、サイバー攻撃の被害にあうと、個人情報・機密情報の漏洩、甚大な経済的損失、法的コンプライアンスの違反など、多くの人々や企業に影響を及ぼします。
リスクに対処するためには、従業員ひとりひとりがリスクを理解し、適切なセキュリティ対策を講じることが非常に重要です。
以下に代表的なサイバーセキュリティリスクを解説していますので、理解を深めるのにお役立てください。
データ漏洩
個人情報や機密情報が悪意のある攻撃者に流出することを指します。特に、クラウドサービスの権限設定が適切に行われていない場合、第三者による不正アクセスが容易になります。最近では、企業の顧客情報が漏洩し、大きな社会問題となっているケースもあります。マルウェア
ウイルスやトロイの木馬など、悪意のあるソフトウェアによってデバイスが感染し、操作が難しくなったり、情報が盗まれたりするリスクがあります。特に、無防備なユーザーを狙ったフィッシングメールでは、実在する企業や人物になりすまして受信者から情報を盗むため注意が必要です。
また、昨今は特定の企業や組織をターゲットにし、メールやWebサイトからマルウェアに感染させる「標的型攻撃」も横行しています。有名な方法に「標的型攻撃メール」があり、メールの添付ファイルやURLリンクを開くことで、悪意あるプログラムを強制インストール(感染)させる手段です。ランサムウェア
重要なデータが暗号化され、元に戻すためには身代金を支払わなければならない攻撃手法です。このリスクは特にビジネスに大きなダメージを与えることが多く、被害を受ける前に対策を講じる必要があります。DDoS攻撃
多数の端末から大量のパケットをサーバーやネットワークに送信し、過剰な負荷をかけてサービスを停止させる分散型サービス妨害攻撃です。これにより、企業のウェブサイトやシステムがダウンし、業務に支障をきたすことがあります。
-
内部不正
クラウドサービスを利用する従業員やパートナーが、故意または過失により情報漏洩を引き起こしたり、誤操作でデータ損失に繋がったりするリスクがあります。特に、権限を持つ者による不正行為は深刻な問題です。
その他にも、パブリッククラウドサービス特有のサイバーセキュリティリスク(責任分界点の認識不足、設定ミス等)も存在します。
詳しくはサイバーセキュリティにおけるクラウドセキュリティの重要性の解説をご覧ください。
サイバーセキュリティのリスクに対する基本的な対策
サイバーセキュリティのリスクを軽減するためには、以下の基本的な対策を検討する必要があります。今すぐにでも行える対策もあるので、ぜひ試してみてください。
-
強固なパスワードの使用
パスワードを複雑で長いものに設定し、定期的に変更することが重要です。また、同じパスワードを複数のサイトで使うことを避け、また二段階認証(MFA)を有効にすることで安全性を高めることができます。また、データ自体にパスワード(鍵)を設定し、暗号化することも可能です。
-
アクセス制御の設定
情報にアクセスできるユーザーを明確に特定し、必要な権限のみを与えることが重要です。
また、入退社や異動、日本企業で多く見られる組織改編(統廃合)のタイミングでアクセス権を見直すことも忘れずに行いましょう。
-
ソフトウェアの定期的な更新・監査
オペレーティングシステムやアプリケーションのソフトウェアを常に最新の状態に保つことで、セキュリティホールを突かれるリスクを減少させます。また、セキュリティポリシーやアクセスログを定期的に監査し、不正アクセスや脅威の兆候を早期に発見することも求められます。
-
セキュリティ対策ツールの活用
マルウェアからデバイスやネットワークを保護するためにウイルス対策ソフトを活用することも効果的です。導入の際は、リアルタイムでスキャンを行う機能や自動更新機能を持つソフトを選ぶことが推奨されます。高度な標的型攻撃への対応としては、振る舞い検知やEDRといったより高機能なツールが有効です。
また、昨今はクラウドの普及が拡大しているため、クラウド環境全体を保護する総合的なセキュリティプラットフォームCNAPP*にも注目が集まっています。様々なセキュリティ対策ツールから、自社の環境に応じて必要なツールを取捨選択するようにしましょう。
*CNAPPについてはクラウドセキュリティで話題の「CNAPP」とは?をご覧ください。
-
セキュリティ教育
サイバーセキュリティのリスクを軽減するためには、従業員への教育も欠かせません。サイバー攻撃の実態やその影響について理解を深め、リスクに対する意識を高めることが大切です。フィッシングメールの見分け方やセキュアなパスワードの作成方法など、従業員への研修や教育を通じて、企業全体の防御力を向上させましょう。
当社では、サイバー先進国イスラエルのナレッジを活用した「セキュリティトレーニングサービス」も提供しています。
詳細はセキュリティトレーニングサービスをご覧ください。
まとめ
この記事では、サイバーセキュリティのリスクとその対策について詳しく解説しました。データ漏洩、マルウェア、ランサムウェアといったリスクを理解し、それに対する対策を講じることが安全なデジタル環境を構築するために重要です。
企業はこれらのリスクを真剣に受け止め、セキュリティ対策ツールの活用や専門家へのアウトソーシング、従業員のセキュリティ教育などを行うことで、便利かつ安全なデジタル環境を築いていきましょう。
弊社では、パブリッククラウド環境のセキュリティ対策として純国産CNAPPの提供をしています。あわせてSOCでの運用サポートや、企業全体のセキュリティリテラシーの底上げを図るセキュリティ教育プログラムもご好評いただいております。